文学部日本語日本文化学科および外国語コミュニケーション学科の日本語教育プログラムには必修科目として「日本語教育の諸問題」が用意されています。日本国内を中心に日本語教育が必要なさまざまな現場や、そこでの取り組み、教え方などについて、複数のゲスト講師の講義を織り交ぜながら考えます。
6月には、田辺淳子先生(愛知学院大学)と渡部真由美先生をお招きし、外国人介護職向けの専門日本語教育と、地域に根差した生活者・子どもたちへの日本語教育についてお話いただきました。
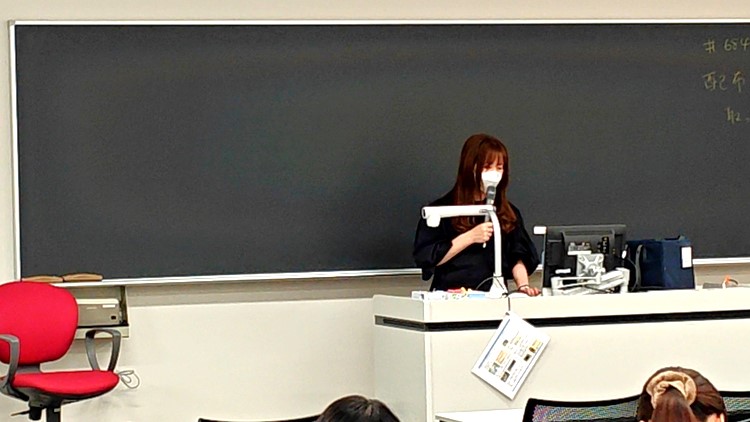
田辺先生は、高齢化社会における外国人介護職の重要性と、彼らが直面する言語的課題についてお話されました。「まれ」「引き戸」といった日常語、オノマトペ、高齢者への声かけ、敬語とタメ口の使い分けなど、介護現場特有の言語・文化的困難を具体例で説明し、専門日本語教育の必要性を強調されました。
学生からは「普段何気なく使う言葉も外国人には難しい」という気づきや、学習者の心理への共感が寄せられました。また、外国人介護職が日本社会にとって不可欠な存在であることを再認識する機会となりました。
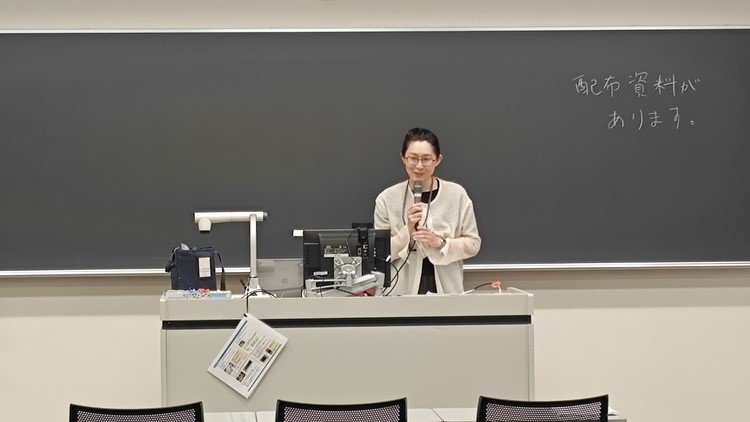
渡部先生は、日本に暮らす外国人、特に子どもたちの日本語教育の現状と課題についてお話されました。畑作業や公共交通機関の利用、防災訓練といった課外活動を積極的に取り入れることで、実生活に必要な知識や文化を体験的に習得し、学習者の自信を育む取り組みを紹介されました。また、外国人の子どもたちが直面する文化的ギャップや不就学問題、NPOやボランティア団体の役割についても言及されました。
学生は「実生活に根差した日本語教育の必要性」や「防災教育の重要性」を実感し、地域で活動する支援者への敬意を深める一方、公的支援の不足という課題も認識しました。
今回のゲスト講義は、日本語教育が現代社会の課題解決に貢献することを学生が実感する機会となりました。多くの学生が、その専門性と社会貢献性を理解し、将来のキャリアを考えるきっかけになったようです。
また、これに先立つ4月には、日本語教師が多く活躍する機関の先生をお呼びし、教材開発や日本語教師としてのキャリアについてもお話いただいています。前期の間に、あわせて3名の多様な先生方の活躍を知ることができました。
本学の日本語教育プログラムは、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等」として確認されており、日本語教員試験のうち「基礎試験」が免除され、「応用試験」の合格のみで、「登録日本語教員」の資格が得られます。
詳細については、2024年4月11日に掲載したお知らせ「『日本語教育プログラム』が国家資格『登録日本語教員』取得のための経過措置対象として確認」をご覧ください。
